人はなぜ戦争をするのか〜歴史を学ぶことで見えた、平和の土台〜
1. なぜ?という問いから始まった学び
皆さんは、心の奥にしまい込んで「いつか考えよう」と先送りしてきた疑問はありませんか?
僕には、この45年間ずっと避けてきた疑問がありました。
――「人はなぜ戦争をするのか」
広島で育つと、戦争や原爆は毎年必ず巡り会うテーマでした。「今が平和でよかったね」と安心する教育を受けて育った一方で、中東の戦争、9.11、ウクライナとロシアの戦争、北朝鮮のミサイル発射など、世界で起きる争いを目にするたび、胸が苦しくなり、「なぜ?」という声が湧き上がるのです。
2. 学びの中で最初に驚いたこと
学校で教わった「太平洋戦争」はこうでした。
ハワイの真珠湾を日本軍が奇襲し、アメリカを怒らせて全面戦争となる。沖縄を占領され、広島・長崎に原子爆弾が落ち、日本は無条件降伏した――と。
でも、ここには大きな疑問が抜けています。
――なぜ、日本は真珠湾を攻撃しなくてはならなかったのか?
――なぜ、大国アメリカを敵に回す選択をしたのか?
僕が学びの中で最初に驚いたのは、日本が世界で最初に「人種差別をやめよう」と声を上げ、アジアの植民地を解放するために戦ったという事実でした。
――だからこそ、この戦争は「大東亜戦争」と呼ばれるのだと、ようやく理解できました。
3. これまでの思い込みとのギャップ
これまで、僕は日本はアジアに侵攻し、自国の領土拡大のために戦争を進めたと思い込んでいました。しかし歴史の事実は違いました。
日本は当時の理不尽な世界に「NO!」を突きつけ、一人で険しい戦いの道を進んでいたのです。
その事実に気づくまでにも違和感はありました。
侵略者が特攻などするのか?
特攻隊の遺書や笑顔の写真は侵略者のものなのか?
いや、違う――そんなはずはない。
日本は世界のスタンダードを壊そうとし、それを脅威に感じた大国たちはシナリオを描き、罠に嵌めました。
罠にハマった日本は、大きな渦に抗う術もなく、この戦いを突き進むことになったのです。
4. 個人的な体験と学びのつながり
日本が世界で最初に人種差別をやめようとした国――僕はそこに大きな誇りを感じます。
自分もその日本人の一人だと思うと背筋が伸びます。
中学生の頃、同級生に保育園から一緒だった小児麻痺の子がいました。
しかし、よく知らない別の小学校から集まった同級生たちは、彼の喋り方を真似て笑っていました。
僕はどうしたか――後ずさったのです。彼から距離を置いてしまった。自分も一緒に笑われるのが嫌だったからです。
思い出すたび、涙が出るほど悔しくなります。自分自身に。
なぜあの時、彼に寄り添えなかったのか。
今ならどう行動するのか――わかりません。でも、考えることができます。考え、行動に移せるよう努力することができます。
小さな前進かもしれませんが、中学生だった僕に言ってあげたい。大丈夫だ、と。
5. 学びを日常に活かす
気をつけたいのは、この記事で「日本は正義だった」「間違っていなかった」と結論づけることではありません。
確かに、御先祖様は戦わなければ家族や国、文化を守れない――そんな崖っぷちに追い込まれて戦ってくださったのです。
大切なのは、歴史を捻じ曲げるのではなく、命をかけて戦った方々の平和への願いと誇りを、今を生きる僕たちが心の土台として携えて生きることです。
強さや裕福さを求めるのではなく、互いに思いやり、困っている人には手を差し伸べ、辛い時には助けを呼び、憎しみ合うことなく日々を積み重ねる――そうして互いに笑い合える今を作ることこそ、僕たちの使命だと思います。
6. 学びの継続と仲間との対話
僕はまだまだ学びの途中ですが、自分自身で歴史の事実をかき集め学ぶことは、自分との対話でもあり、アイデンティティに深く関わる行為です。
日本に生まれて生きていることの奇跡的体験や、先人が命をかけて願った平和の中に存在している有り難さに気づくと、周りの全てが感謝で溢れているはずです。
もちろん、これはあくまで僕個人の見解です。
一人ひとり違った意見や見方があるのは当然のことです。
特に若い方には、一人で学ぶだけでなく、仲間と議論したり情報を共有し合ったりして異なる考えに触れることをおすすめします。
そうやって優しい和が少しずつ広がっていくことを願っています。
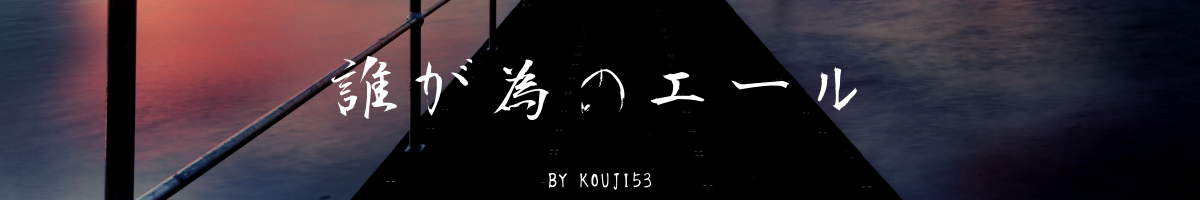
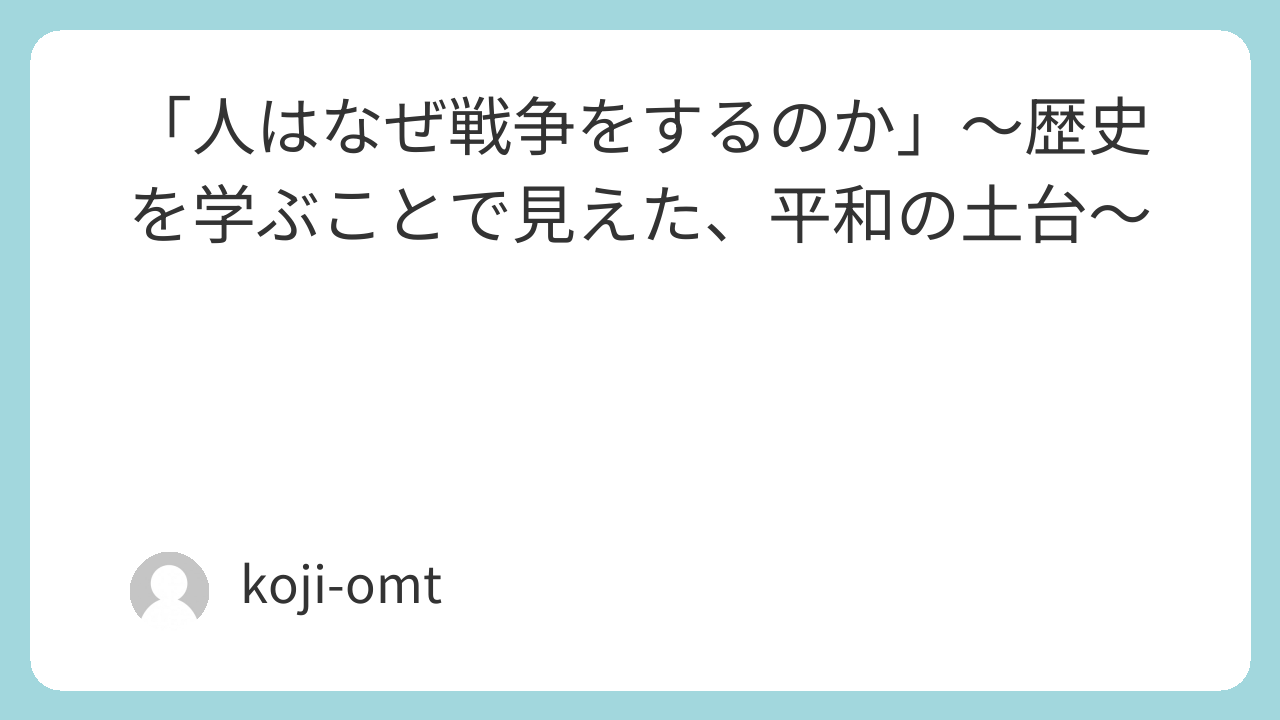
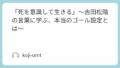
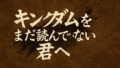
コメント