コーヒーを淹れる、非効率な時間が教えてくれる生と死
① はじめに
僕は毎朝、コーヒーを淹れる。
豆の知識が豊富なわけでもなく、味に強いこだわりがあるわけでもない。もちろんコーヒーは好きだし、落ち着いて飲むひとときはかけがえのない時間だと思っている。
朝、コーヒーを淹れると家の中が香りに包まれる。
2階から階段を降りてくる妻が、「いい香り」と言って微笑む。
その表情を見るのが嬉しくて、僕はコーヒーを淹れる。
豆は、妻がネットで選んでくれることが多い。
僕はその豆がある限り、毎朝コーヒーを淹れる。
たかがコーヒー、と思う人もいるかもしれない。
確かに、ただコーヒーを飲むことが目的なら、僕のやり方は効率が悪い。
でも、その“非効率な行動と時間”こそが、僕にとって生き方を考えるための大切なルーティンになっていたんだ。
② 「香り」が心を整えてくれる
毎日飽きずにコーヒーを淹れ続けていられるのは、香りのおかげだ。
ドリップした瞬間に広がる、あの優しさに満ちた香り。
幸福感を“香り”で表現するとしたら、きっとあれになると思う。
リビングいっぱいに広がるコーヒーの香りに包まれると、
「今、ここにいる」という実感がじわじわと心に浸透してくる。
その空気を吸い込めるだけ吸い込んで、心を満たしていく。
③ 「時間=命」という考え方を思考の土台に
以前、ラジオで「時間は過去から未来へ流れていくものではなく、未来から“今”へと向かってくるものだ」という話を聴いて、ハッとした。
さらに思い出したのが、「人間は、生まれてから死ぬまでの心臓の鼓動の回数が決まっている」という話。
その二つを重ねたとき、僕の中で何かが繋がった。
未来からやってくる時間。そして、生まれた瞬間から刻まれる心臓の鼓動。
そのどちらも、確実に「死」へと向かっている。
生きるという行為は、ただ目の前の時間を過ごすことじゃなくて、
見えない終点に向かって、静かにカウントダウンされている行為なんだと気づかされた。
④ 「死」と隣り合わせにある毎日
何気なく過ごしていた日常に、「明日が確実に来るとは限らない」という前提が加わることで、
時間や命という言葉の重みが、急にリアルに感じられるようになった。
「死」を意識すると、「今」という瞬間がくっきりと輪郭を持ち始める。
たとえば、コーヒーを淹れるという行為一つとっても、
ただ力いっぱい集中して行えばいいというものではなく、
そのとき自分がどんな気持ちで、どんな心持ちで「今」を迎えているかに目を向けたくなる。
神様がこの世界を作ったとしたら、
その視点から見たとき、人ひとりの一生にはどんな意味があるんだろう。
僕たちが与えられた「時間」も、「命」と同じく、神様からのギフトなのかもしれない。
⑤ 朝のルーティンは、生きるための儀式
目が覚めたらまず水を飲み、
コーヒーを淹れながら「今日も素晴らしい日になる」と自分に言い聞かせる。
それは、ただ繰り返すだけのルーティンじゃない。
心臓の鼓動とともに常に“今”は更新されていて、その都度、命もまた刻まれている。
だからこの習慣は、効率では測れない。
むしろ「心を整える儀式」と言ってもいい。
自分は、あと何回このルーティンを重ねられるだろう?
朝のコーヒー時間は、死との距離を測るための静かな時間でもある。
⑥ 「誰かのために」という生き方の選択
このような思考の背景には、転職という人生の岐路があった。
自分でいるために、「誰かの役に立ちたい」という思いがあった。
自分の時間と命を、誰かの幸せのために使いたかった。
そう思える仕事に就けたことで、自分を少し肯定できた気がした。
この精神の安定のあり方も、僕にとっては大切なことだ。
もちろん、これからの未来に、また不安や困難は待っているかもしれない。
それでも、生きている限り「誰かのために命を使う」という問いと、
正面から向き合い続けていこうと覚悟している。
おわりに
どれだけ効率的に技術が発展しても、
「一杯のコーヒーを淹れる時間」が、こんなにも自分の命と深いところでつながっていたとは思いもしなかった。
時間は命。命は、誰かの幸せのためにある。
朝の香りは、人生をよりシンプルにしてくれることに、そっと気づかせてくれたのだ。
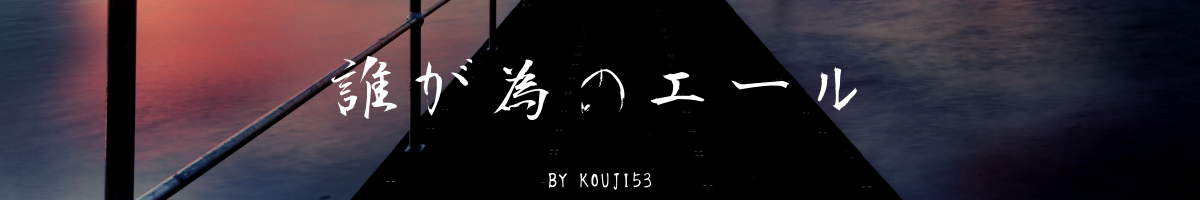

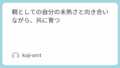
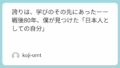
コメント