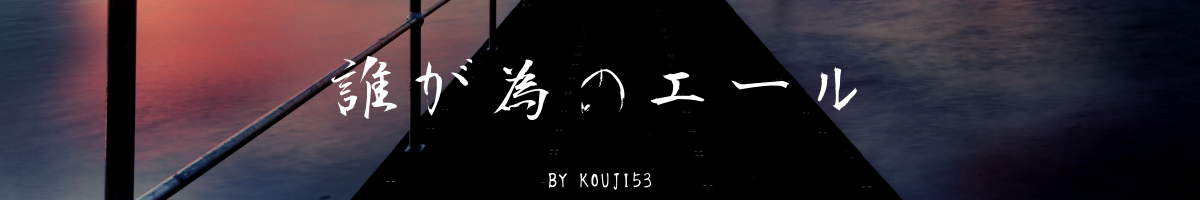【編集注記】本稿は2025年10月10日時点で放送された第1話および番組公式の公表情報をもとに執筆しています。以降の展開に触れる箇所は、あくまで第1話の描写から導く解釈・期待であり断定ではありません。最新情報は番組公式をご確認ください。
女性目線で見る『じゃあ、あんたが作ってみろよ』——“自分を取り戻す”という愛の形
結婚してしばらく経つと、「愛してる」よりも「お弁当ありがとう」のほうが重く響く日があります。
そして、台所に立ちながらふと考えるんです。——この味噌汁、私の人生のどこに位置してるんだろう?って。
TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』を観て、私は思わず笑ってしまいました。あぁ、これ、うちの話かもしれないなって。
山岸鮎美(夏帆)は、愛する人のために“ちゃんとした女性”であろうと頑張り続けた人。けれど気づけば、彼女の「ありがとう」も「おかえり」も、全部が“作業”になっていた。その表情の奥に、「誰が私を気づいてくれるの?」という小さな祈りが見える。
私もかつて、そんな夜を過ごしたことがあります。仕事から帰って、夕飯を作って、洗濯を回して、ソファに座った瞬間に聞こえる「俺の靴下どこ?」。あのときの私は、きっと“愛していた”けれど、“愛されてる実感”は遠かった。
だからこそ、鮎美がプロポーズを断る場面に胸の奥がじんわりした。それは決して冷たさじゃない。彼女の中でようやく芽生えた、「私を諦めないためのYES」だった。
このドラマは、怒りでも復讐でもない。“自分を大切にする”という、ごく静かで、でもとびきり勇敢なラブストーリー。優しさに疲れたすべての人に、鮎美の声が届けばいい。そんな気持ちで、この稿を書いています。
第1章 「愛される女」から「自分を生きる女」へ
結婚生活って、不思議なもので。
最初のうちは「相手のために頑張れる私」が、ちょっと誇らしかったりする。
朝ごはんの卵焼きがきれいに巻けた日なんて、
それだけで“愛されてる実感”を感じられた。
でも、ある日ふと気づく。
“頑張れる私”ばかりが残って、“私”そのものがどこかへ消えている。
誰も責めていないのに、なぜか息が苦しい。
鮎美(夏帆)の姿には、そんな“優しさの摩耗”が滲んでいた。
彼女は、誰よりも気が利く。
夫の好みも、仕事の優先順位も、まわりの空気も読める。
でも、自分の心だけは読めなくなっていた。
そのバランスの崩れが、女性を一番静かに壊していく。
プロポーズの場面。
鮎美は、少し間をおいてから“ごめん”と答える。
あの一瞬、画面がふっと静まり返る。
私は思わず呼吸を止めた。
彼女が断ったのは、結婚じゃなくて、「自分を見失う未来」だったのだ。
その選択は、決してドラマチックじゃない。
むしろ現実的で、痛いくらいに現代的。
家事も仕事も恋も、「できる人」ほど我慢がうまくなってしまうから。
自分を犠牲にしてでも関係を保つ——それを“愛”と勘違いしてしまう。
私はこれまで多くの現場で、そういう女性たちを見てきた。
撮影の合間に、疲れた笑顔で「大丈夫ですよ」と言うスタッフたち。
でも、本当は大丈夫じゃなかった。
彼女たちが抱えていたのは“誰にも見えない疲労”だった。
鮎美の決断は、その「大丈夫」の呪いを解く行為だと思う。
誰かに許可をもらわなくても、自分を生きていい。
“愛される”ための努力をやめて、“生きる”ための努力を選ぶ。
その勇気を、彼女は静かに見せてくれた。
そして、それは決して男性を責める物語ではない。
鮎美の“NO”は、戦いではなく、対話の始まり。
「私はもう、私を諦めたくない」——
その言葉が、あの部屋の空気を一変させた気がした。
第2章 ケアの非対称性——“やってあげる”の罠
「やってあげたい」と思う気持ちは、愛のはじまりだ。
でも、「やってあげなきゃ」と思いはじめた瞬間、愛は少しずつ形を変える。
鮎美(夏帆)は、まさにその境界で立ち止まっていた。
朝ごはんの準備、洗濯、メッセージの返信、誕生日の段取り。
それらを“自然にできること”としてこなすたびに、
彼女の「私」は薄くなっていく。
一方で、勝男(竹内涼真)は悪気がない。
だからこそ、ややこしい。
“やってもらう側”が、それをケアとすら感じていない。
無自覚のまま、感謝も労いもなく、ただ“日常”として受け取っている。
ここにあるのは、暴力ではなく構造だ。
家事という行為の中に、“見えないヒエラルキー”が埋め込まれている。
それは「女性が自然に回してくれる世界」という前提の上に成り立っている。
鮎美は、その前提の重さに気づいてしまった。
仕事の帰りにスーパーで値引きシールを探し、
洗濯機を回しながら明日の献立を考える。
そんな日々の繰り返しを“頑張ってるね”の一言で終わらせる社会。
あの沈黙こそが、彼女を最も疲弊させていた。
私も、取材で似た話を何度も聞いた。
「夫に家事をお願いしたら、“手伝った”って言われて、
もうそれ以上頼む気にならなかったんです」と笑う女性。
その笑顔の奥に、少しだけ諦めが混ざっていた。
鮎美も同じだった。
彼女が怒っていたのは、手伝わないことじゃない。
“分かろうとしないこと”だった。
「作ってみろよ」という台詞の本当の意味は、
「あなたにも、私の毎日を感じてほしい」という呼びかけなのだ。
家事の分担を超えたテーマ——それは“想像力の再配分”。
ドラマはそれを真正面から描いている。
鮎美が沈黙を破る瞬間、
彼女の中で“やってあげる女”は終わり、
“一緒に生きる女”が始まる。
私たちもまた、日常のどこかで同じ問いを突きつけられている。
「やってあげる」から「一緒にやろう」へ——。
たったそれだけの言葉の変化が、
愛をこんなにも優しく強くするのだと、このドラマが教えてくれる。
第3章 渚という光——「自分の機嫌を取る」という新しい愛
人生のどこかで、誰もが一度は「渚」みたいな人に救われている気がします。
ちゃんと話を聞いてくれて、でも説教はしない。
コーヒーを差し出すタイミングだけ、絶妙にうまい。
鮎美(夏帆)にとっての渚(サーヤ)は、まさにそんな存在でした。
彼女は「正しいこと」を教えない。
ただ、鮎美が泣くことも笑うことも、どちらも“いいね”と受け入れてくれる。
その包み方が、少し風のようで、少し太陽みたいで。
渚の口癖は、「自分の機嫌は、自分で取る」。
最初に聞いたとき、私は思わず笑ってしまいました。
だって、それって簡単そうで、いちばん難しいことだから。
家事も恋愛も人間関係も、私たちはつい「相手の機嫌」を優先してしまう。
彼が不機嫌なら、空気を読む。
子どもが泣いたら、なだめる。
でも、自分が泣きたいときには“我慢”を選ぶ。
女性が背負いすぎる“空気の管理”の苦しさを、渚は軽やかにほどいてくれる。
鮎美が渚の家を訪ねるシーン。
テーブルの上には花とクッキーと紅茶。
その並びの自然さが、彼女の生き方そのものだった。
「整えること」と「飾らないこと」の間に、渚の哲学がある。
私はこのシーンを観ながら、ある取材を思い出しました。
シングルマザーの女性がこう言っていたのです。
「自分のことを後回しにしすぎると、誰かに優しくする余裕もなくなるんです」
その言葉が、渚の笑顔と重なりました。
渚は、鮎美に“幸せの定義”を押しつけない。
「それでいいんじゃない?」の一言に、どれほどの肯定が詰まっているか。
ドラマの中で最も小さなセリフが、いちばん大きな救いになる瞬間です。
そして気づくのです。
鮎美が変わったのは、恋人との衝突ではなく、
“女性同士の共鳴”に触れたからだと。
渚が示したのは、「戦わない強さ」「自分を許す優しさ」でした。
この関係性の描写は、TBSドラマらしい繊細さ。
女性が女性を“救う”というより、“回復させ合う”構図。
競わない、比べない、教えない——。
そんな新しい愛のかたちが、ここにある。
鮎美が帰り道で少しだけ空を見上げる。
あの一瞬、画面の光が柔らかく変わる。
それは、希望の表情でも決意の顔でもない。
ただ、少しだけ“自分に戻った”人の表情だった。
それで十分だ、と渚なら言うでしょう。
第4章 鮎美の沈黙が語るもの——「我慢」という言葉の暴力
我慢って、ほんとうはやさしさの変形なのかもしれません。
相手を思って飲み込む。波風を立てたくなくて笑う。
でもその「我慢」が続くと、やがて心は、
誰にも触れられない場所に閉じ込められてしまう。
鮎美(夏帆)が勝男(竹内涼真)に向けて言葉を飲み込むたび、
私は、あの沈黙の重さに息を詰まらせました。
ドラマの中で、彼女は怒鳴らない。泣き叫ばない。
代わりに、少し長いまばたきをする。
その一拍に、彼女の人生が全部つまっている。
「我慢」という言葉は、昔から褒め言葉のように使われてきました。
“よく我慢したね”“大人になったね”。
でも実際は、それがどれほど危うい称賛かを、
私たちはまだうまく言葉にできていない。
ある主婦の方が、取材のときに言っていました。
「夫が変わるのを待ってたら、自分が消えちゃいそうになったんです」
そのとき、彼女の声は震えていなかった。
けれどその穏やかさが、いちばん痛かった。
鮎美も同じです。
彼女の「ごめん」は謝罪ではなく、悲鳴だった。
“怒ってもいいのに怒れない自分”を、
彼女自身がいちばん責めていた。
その優しさが、彼女をゆっくりと蝕んでいったのです。
映像としても、この章の演出は見事でした。
音が極端に少なく、照明は白昼の光を抑えたグレイッシュトーン。
まるで世界全体が、彼女の沈黙に耳を澄ませているようでした。
その中で一瞬だけ鳴るカトラリーの音。
あの小さな金属音が、「もう限界」という心の声に聞こえたのは、
私だけじゃないと思う。
“我慢”の根っこにあるのは、愛を失いたくないという恐れです。
でも、本当に愛があるなら、沈黙しなくてもいい。
鮎美がそれに気づくまでにかかった時間こそ、
多くの女性が抱える“見えない労働”の象徴だと感じます。
そして、あのシーンのあとでようやく彼女は小さく笑う。
それは「もういい」と諦める笑顔ではなく、
「もう私の番だ」という、再生の始まりの笑顔でした。
我慢をやめることは、わがままじゃない。
自分の人生を取り戻すための、最初の呼吸なんです。
鮎美の沈黙は、壊れる音ではなく、生まれ直す音だったのだと、私は思う。
第5章 愛を“終わらせない勇気”——別れの再定義
「もう終わりにしよう」——この言葉ほど誤解されるフレーズはないと思う。
多くの人はそれを“関係の断絶”と受け取るけれど、
鮎美(夏帆)にとってそれは、「私を取り戻すための再出発」だった。
彼女が勝男(竹内涼真)に別れを告げるシーン。
空気は穏やかなのに、心臓だけが少し速く打っているような、
あの独特の緊張が画面を支配していた。
彼女の目は、涙ではなく、静かな確信で光っていた。
“終わらせる”ことは、負けじゃない。
むしろ、愛をまっすぐに見つめる力だ。
一度壊さなければ、もう一度築くこともできない。
鮎美は、その痛みを選んだ。
それは、誰かを責めるためではなく、
“本当の対話”を取り戻すための勇気だった。
ドラマを観ながら、私はある離婚経験者の言葉を思い出した。
「別れてからのほうが、彼をちゃんと理解できた気がするんです」
それは未練ではなく、成熟の言葉だった。
一度“愛する”を手放したからこそ見えた距離感。
鮎美の選択も、まさにその境地にある。
勝男はきっと、彼女を失って初めて気づく。
“誰かに作ってもらう生活”と、“誰かと作る生活”は違うということを。
この物語の真のテーマは、「終わり方」ではなく「関わり方」なのだ。
鮎美のラストの微笑みを思い出す。
あれは“さよなら”ではなく、“ありがとう”の表情だった。
彼女は彼の幸せを願いながら、自分の幸せに向かって歩き出す。
別れを終わりにしない、優しい革命。
私たちの多くは、関係を保つために自分を削ってしまう。
でも、本当に誰かを愛するというのは、
「一緒にいること」よりも、「相手を信じて離れること」なのかもしれない。
鮎美の旅は、恋の終わりではなく、成熟の始まり。
愛を手放す勇気が、彼女に“自分を抱きしめる自由”を与えた。
その自由こそが、愛のいちばん静かな完成形なのだと、私は思う。
第6章 音楽と光——「できることだけでいい」と言ってくれた歌
第1話の終盤〜エンドカード/番組素材でも印象的に用いられる
Chilli Beans.「that’s all i can do」。初めて耳にしたとき、胸の奥がすとんと静かになった。
鮎美(夏帆)の表情と、このフレーズが同じ呼吸で動いているように感じた。
♪ that’s all i can do——それが私にできるすべて。
たった一行なのに、どれほどの肯定が詰まっているだろう。
“もっと頑張らなきゃ”“ちゃんとしなきゃ”と
自分を追い込み続けた女性たちに向けて、
このフレーズは、そっとブレーキをかけてくれる。
鮎美が再生していく物語の終盤で、この曲が流れるタイミングが完璧だった。
キッチンに差し込む朝の光、整っていない食卓、
そして一人分のカップから立ち上る湯気。
それらがすべて、「それでいいんだよ」と語りかけてくる。
演出面では、光のトーンが物語とともに変化していくのが印象的だ。
序盤の冷たい白色光が、終盤には柔らかい琥珀色に変わる。
鮎美が「我慢」から「自分を赦す」へと変わるプロセスを、
光そのものが演じていた。
そして、音。
劇伴の音数は少なく、ほとんどがピアノと空気音。
その余白が、彼女の再生の“間”を作っていた。
音が少ないほど、呼吸の音が聞こえる。
その呼吸こそが、生き直す音なのだ。
私はこの曲を何度も聴き返しながら、ある夜のことを思い出した。
自分のキャリアと家庭のバランスを崩して、
ソファの上で泣きながら「もう、これ以上は無理」と思った夜。
そのとき、頭の中でこのフレーズが浮かんだ——
“That’s all I can do.”
できることを、できるぶんだけ。
それで十分じゃないかと、あのときの私は少しだけ救われた。
鮎美もきっと、同じように思ったはずだ。
「誰かの理想を生きるのは、もうやめよう」と。
光の中で彼女が見せたあの小さな笑顔は、
まるで音楽の余韻そのものだった。
この主題歌と演出が教えてくれるのは、
完璧じゃなくても、生きていていいという肯定。
そして、失敗も欠けも含めて“私”なのだという静かな誇り。
ドラマが終わったあと、私はしばらく画面を見つめていた。
そこにあったのは悲しみではなく、
“大丈夫”という小さな息遣いだった。
Chilli Beans.「that’s all i can do」 のSpotifyトラック:
Spotify
This is LAST(主題歌「シェイプシフター」担当アーティスト) のSpotifyアーティストページ:
Spotify
第7章 原作との距離——“怒り”から“癒し”へ
原作の『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(谷口菜津子)は、
もっと鋭く、もっと剥き出しの物語だった。
ページをめくるたびに、
「これが現実だ」と突きつけられるような切実さがあった。
台詞は刃物のように尖っていて、
そこには、笑いに変えられないほどの“怒り”が流れていた。
一方で、TBSドラマ版はそのトーンを少し変えた。
角を丸めたというより、痛みを抱きしめる方向へ舵を切った。
同じテーマを描きながらも、
“怒り”ではなく“癒し”を選んだ脚本の勇気に、私は深くうなずいた。
原作では、主人公が声を荒げる場面が象徴的だ。
「なんで私ばっかり!」
その叫びは、社会構造への直接的な抗議であり、
同時に“諦めたくない”という祈りでもあった。
対してドラマでは、同じ思いを、沈黙と優しいユーモアで包んでいる。
怒りを外へ放つのではなく、
痛みを内側で熟成させて光に変えていく描き方だ。
それはきっと、時代の空気の違いでもある。
SNSで声を上げることが“戦い”だった時代から、
“癒す”ことが新しい抵抗になりつつある今へ。
ドラマ版の鮎美は、怒らない。
その静けさの中で、彼女の意志はより強く見える。
谷口菜津子の原作が投げかけたのは、「分かってよ」という痛烈な問い。
一方で、TBS版はこう語りかける——
「分からなくても、一緒にいよう」。
このわずかな差が、作品全体の温度を決定づけている。
映像と紙のちがいは、“時間の流れ”だと思う。
コマ割りでは切り取れない呼吸を、ドラマは音と光で表現できる。
鮎美が小さく息を吐くその瞬間、
視聴者は彼女の心の揺らぎを“体で”感じる。
だから、ドラマ版の優しさは決して弱さではない。
それは、感情の成熟としての優しさなのだ。
“怒り”は、物語を動かす火。
“癒し”は、その火を絶やさない灯。
原作とドラマは、違う道を歩きながら、
最後は同じ場所——「自分を取り戻す」——にたどり着く。
どちらの物語にも、嘘はない。
ただ、ドラマ版が選んだのは、「赦す」という名の革命だった。
怒りを手放すのではなく、それを抱いたまま歩いていく強さ。
それが、今の時代の“優しさのかたち”なのだと思う。
第8章 自分を取り戻すという愛の形
「あなたを愛していたけれど、もう私を見失いたくない」——。
鮎美(夏帆)の旅をひとことで言うなら、きっとこの言葉になる。
彼女の物語は、恋愛の再生ではなく自己への帰還だった。
誰かの期待に応える愛ではなく、
“自分を尊重しながら誰かを愛する”という、
まだ名前のない新しい形を描いていた。
第1話の静かな食卓のショットが忘れられない。派手な演出はない。
ただ、一人分の箸や、湯気の立つカップが画面の余白に置かれているだけ。
それでも、その静けさの中に、これまでのすべてが息づいているように見えた。
物語がこの先どこへ向かうとしても、私はあの“静かな肯定”が軸になると信じている。
光は穏やかで、音は少なく、
それでもあの瞬間だけ、世界が彼女を中心に回っているように見えた。
“自分の場所に戻る”ということは、
誰かを排除することではなく、世界と和解することなのだと気づかされる。
私は、長くドラマを見てきて思う。
愛って、いつも“勝ち負け”や“続く・終わる”で語られがちだけれど、
本当の愛は、静かに“在り続ける”ものなんじゃないかと。
そこにいるだけで、誰かが少し救われる。
鮎美が最後に見せた笑顔は、そんな存在の証のようだった。
“自分を取り戻す”ということは、
誰かを置いていくことではない。
むしろ、もう一度、誰かと向き合うための準備だ。
彼女の再生は、社会や恋愛を越えて、
すべての“私たち”に向けられたエールに思えた。
きっと、彼女はこれからも誰かを愛する。
でも、その愛は、かつてのように“我慢”ではなく“選択”になる。
それが、このドラマの優しさの核心。
愛とは、相手のために生きることではなく、
一緒にいられるように自分を大切にすることなのだ。
画面が暗転し、エンドロールが流れる。
けれど物語は、終わらない。
私たちの誰かが、またキッチンに立って、
新しい「作ってみろよ」を始めるのだと思う。
その瞬間、ドラマは現実になる。
鮎美の物語は、私たちに問いかけている。
「あなたは、今日、自分のことを大切にできましたか?」
その問いに、ゆっくりと“はい”と答えられるように。
今日も私は、湯気の立つカップを両手で包みながら、
この物語の続きを、生きていこうと思う。
まだ第1話しか放送されていない今、物語はようやく火が灯ったばかり。
鮎美と勝男がどんな関係を築いていくのか、渚がどんな風に彼女を導くのか——。
その答えはきっと、派手な展開の中ではなく、何気ない日常の呼吸の中に隠れているはずです。
このドラマは、誰かを裁く物語ではありません。
“分かってもらえない”という孤独を、“分かり合えなくても隣にいる”という優しさへと変えていく物語。
だから、これからの毎週火曜が、少しだけ自分を見つめ直す夜になるといいなと思います。
私自身、ドラマを観ながら、仕事や家庭、愛する人との距離をもう一度見つめ直してしまいました。
鮎美の「作ってみろよ」は、彼女だけでなく、私たち自身への挑戦状なのかもしれません。
——あなたは、いま、どんな“自分”を作っていますか?
もし少しでも心が動いたなら、それだけでこのドラマの意味は始まっている。
次のエピソードで、鮎美たちがどんな一歩を踏み出すのか。
そして、私たちがその一歩をどう受け止めるのか。
「作る」ことの本当の意味を、共に見届けていきましょう。