男性目線で見る『じゃあ、あんたが作ってみろよ』——“化石男”が気づくまで:勝ち負けでは測れない家事と愛
「料理は女が作って当たり前」——その言葉を、私は撮影現場でも、家庭の食卓でも、何度も耳にしてきた。
ほんの冗談のつもりで口にした言葉が、誰かの胸の奥を冷たく凍らせていくのを、私は何度も見た。
そんな“あたりまえ”が崩れる音を、TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は真正面から映している。
夏帆と竹内涼真、ふたりの演技は、愛と生活の摩擦音をあまりにもリアルに響かせる。
誰かと一緒に生きるとは、相手を理解することではなく、「理解できない痛みを想像し続けること」なのだと、私は思い知らされた。
私自身、助監督時代に何度も見た。撮影の合間、冷えた弁当を食べながら、女性スタッフがこぼしたため息。
「うちじゃ、料理してる時間なんてないのに、夫は“仕事してきた俺のほうが疲れてる”って言うんです」
その小さな嘆きを、社会はどれほど見逃してきたのだろう。
だからこそ、このドラマのタイトルが突き刺さる。
「じゃあ、あんたが作ってみろよ」——それは挑発じゃない。
愛の名を借りた不平等への、静かな反乱だ。
男性目線で見ると、この物語は“反省”ではなく“学習”の物語になる。
海老原勝男という“化石男”が、愛する人を通して時代に追いついていくその過程は、どこかで私たち自身の姿でもある。
本稿では、制作現場と批評の両方の視点から、このドラマが描く「ケア」「プライド」「負けたくない」の感情設計を紐解いていく。
愛とは勝つことでも、譲ることでもない。——“同じ痛みを分け合えること”、その尊さを語りたい。
第1章 作品の骨格:何が“当たり前”を揺らすのか
このドラマを見て、最初に思い出したのは、撮影現場で耳にした女性スタッフの小さな独り言だった。
「うちの夫、料理しても“手伝った”って言うんですよね」
その言葉の裏に滲んでいたのは、怒りでも悲しみでもなく、長年かけて擦り切れた諦めだった。
『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、その擦り切れた日常に“もう一度、ちゃんと向き合ってみよう”と投げかける物語だ。
舞台は東京の一軒家。山岸鮎美(夏帆)と海老原勝男(竹内涼真)、一見すると「理想的なカップル」。
けれど、鮎美の“ごめん、もう無理”という一言が、二人の関係の歯車を止める。
第1話の象徴は、勝男が初めて挑む筑前煮。
彼にとっては、ただの料理。しかし視聴者には、「見えない家事を見える化する儀式」として映る。
食材を洗い、皮をむき、火加減を探る。その一つひとつの工程が、彼の価値観を少しずつ剥いでいく。
家事の苦労を“知らなかった”男性が、作業を通じて初めて気づく——
生活を回すことは、戦うことよりずっと難しいという事実。
この瞬間、物語は単なる男女のすれ違いを超えて、「社会が見落としてきた感情の回復劇」へと変わる。
第2章 セリフの解像度:「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の本意
タイトルにもなっているこのセリフを、私は初めて耳にしたとき、胸の奥が少し痛んだ。
私も昔、誰かに似た言葉を浴びせたことがある。疲れて、認められなくて、少しだけ自分が正しいと思いたくて。
だからこそ、この「じゃあ、あんたが作ってみろよ」という言葉の強さと優しさを知っている。
それは怒りの爆発ではなく、“理解されない痛みを共有してほしい”という、最後のSOSだ。
ドラマの中で、鮎美はこのセリフをまだ放ってはいない——彼女の目には涙よりも、諦めの静けさが映る。
視聴者はその沈黙を通して、彼女がどれほど長い間「黙って耐えてきたか」を悟る。
そして同時に、勝男が感じる“居たたまれなさ”は、私たち自身の姿でもある。
家事の負担、見えない労働、無意識の支配。
そのすべてが、この一言に凝縮されている。
「作ってみろよ」という言葉は、責めではなく、「同じ場所に立ってくれ」という呼びかけなのだ。
批評家として数多くの作品を見てきたが、これほど“セリフの温度”が変化して聞こえる作品は稀だ。
見る人の立場によって、この台詞はナイフにも、抱擁にもなる。
その揺らぎこそが、このドラマの美しさだと私は思う。
第3章 海老原勝男という“化石男”:変わることを恐れる心の正体
ドラマを見ていて、勝男の姿にどこか既視感を覚えた。
それは、制作現場で出会った数多くの男性スタッフたち——そして、かつての自分自身かもしれない。
「正しさ」は、時に最も便利な盾になる。勝男はその盾を手放せずにいた。
彼の「俺は間違っていない」という信念は、実は“自分を守りたい弱さ”の裏返しだ。
家事も恋愛も、彼にとってはプライドの延長線上にあった。
けれど筑前煮を前にした瞬間、勝男は初めて気づく。
「知らない」ということが、どれほど人を傷つけるかを。
調味料を量り間違え、火加減を失い、片付けに途方に暮れる。
その一つ一つが、彼の中の“無知の壁”を静かに崩していく。
勝男が“作る”という行為を通して直面するのは、まさに沈黙の重さだ。
彼は敗北を通じて初めて人間になる。
ドラマが優れているのは、彼を“改心した男”ではなく、“学び続ける男”として描いている点だ。
第4章 山岸鮎美という女性:愛の名で消耗した心を取り戻すまで
鮎美を見ていると、「優しさは時に自分を削る」という現実に直面させられる。
彼女は愛する人を支えようとするあまり、いつの間にか自分の声を失っていった。
鮎美がプロポーズを断ったのは、決して冷めたからではない。
彼女はようやく気づいたのだ。「愛される私」ではなく、「私を愛する私」でいなければ、生きていけないということに。
渚(サーヤ)の存在が、彼女を救う。説教ではなく、寄り添いで。
「自分の機嫌を取れる人が、いちばん強いよ」——その言葉が、鮎美の心に静かに届く。
夏帆の演技は、痛みと再生を併せ持つ呼吸そのもの。
無表情の中にある微かな笑みが、彼女の決意を物語っていた。
それは、愛の終わりではなく、成熟の始まりだ。
第5章 支線キャラクターが映す「社会という鏡」
このドラマが秀逸なのは、勝男と鮎美の物語を「社会の縮図」として立体的に描いている点だ。
登場人物たちは単なる脇役ではなく、現代の“価値観の断面”を担っている。
たとえば、柏倉椿(中条あやみ)。
仕事では完璧を装うが、プライベートでは常に“誰かにとっての理想像”に縛られている。
その姿は、SNS時代を生きる多くの女性たちの現実だ。
「ちゃんとしていなきゃ」と思うたびに、心の余白が削られていく。
彼女の笑顔は、社会の「演じる女性」たちの仮面を映している。
一方、渚(サーヤ)は対極にいる。
努力よりもバランス、正解よりも感情を優先する女性。
彼女の言葉「自分の機嫌を取れる人が、いちばん強いよ」は、
鮎美だけでなく、視聴者にも突き刺さる。
渚の存在は、癒しではなく“社会が忘れた柔らかさ”の代弁だ。
ミナト(青木柚)はZ世代の観察者として、物語に風穴を開ける。
家事も恋愛も「やって当たり前」とは思わない彼の感覚が、
勝男にとっての「未来のスタンダード」を提示している。
彼の軽やかなリアリズムが、物語全体の呼吸を整える。
そして、南川あみな(杏花)。
勝男を真正面から責めない彼女の態度には、
“変わろうとする人を見守る”という優しさが宿っている。
彼女のまなざしがあるからこそ、このドラマは説教臭くならない。
彼らは皆、「誰かの正義を押しつけない」登場人物たちだ。
その静かな多様性が、この作品を“共感の群像劇”に押し上げている。
第6章 音楽と演出:感情の呼吸をつくるもの
ドラマを構成するのは台詞や演技だけではない。
光と音の“呼吸”こそが、感情の輪郭を決める。
『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の演出陣は、その精度が抜群だ。
主題歌・This is LAST「シェイプシフター」は、まるでこのドラマの哲学を代弁している。
「変わりたい」と叫ぶのではなく、「変わらざるを得ない日常」の中で、
人が少しずつ形を変えていく。その歌詞は勝男の成長のメタファーだ。
Chilli Beans.「that’s all i can do」 のSpotifyトラック:
Spotify
挿入歌・Chilli Beans.「that’s all i can do」は、鮎美の物語線を支える。
“私にできることだけでいい”という潔さが、彼女の静かな再生を包み込む。
この二曲が対を成すことで、「共鳴としての愛」が浮かび上がる。
This is LAST(主題歌「シェイプシフター」担当アーティスト) のSpotifyアーティストページ:
Spotify
映像面では、夕陽のオレンジと白いキッチンライトの対比が印象的だ。
特に筑前煮の湯気を照らす光は、敗北の色ではなく「理解の兆し」として機能している。
照明が感情を語る、非常に繊細な演出設計だ。
感情は、言葉ではなく温度で伝わる。
このドラマは“温度の演出”が見事にできている。
第7章 原作との対話:問いを継ぎ、社会に返す
原作・谷口菜津子による漫画版『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、
日常の小競り合いをユーモアと毒気で描いた社会風刺作だ。
ドラマ版はそのエッセンスを残しながらも、より“感情の地層”を掘り下げている。
漫画が「気づきの瞬間」を提示していたとすれば、
ドラマは「変わっていく過程」を描いている。
つまり、原作が問いを投げ、ドラマがその問いに答えを試みている構造だ。
制作チームは、原作のコメディ要素を薄める代わりに、
社会的文脈(ケア・家事・ジェンダー)を強調した。
だがそれは決して“重くする”改変ではなく、“共に考える装置”への進化だった。
TBS火曜ドラマらしい、社会と娯楽の絶妙な融合がここにある。
原作が“問い”を提示し、ドラマが“対話”を広げる。
その連鎖が、視聴者一人ひとりの「再学習」を促している。
第8章 結語——「作ってみろよ」の先にある希望
「じゃあ、あんたが作ってみろよ」——この言葉を、怒りの叫びではなく、
“共に生きるための招待状”として受け取るとき、
このドラマの意味はまったく違うものになる。
勝男も鮎美も、誰かを打ち負かしたいわけじゃなかった。
ただ、分かってほしかった。分かりたかった。
その小さな欲求のすれ違いが、何年も続く関係の歪みを生んできたのだ。
私たちの社会もまた、そうなのかもしれない。
誰も悪人ではない。ただ、想像力が少し足りない。
だからこそ、このドラマの一言が、時代を静かに動かす。
愛は、つくるものではなく、分かち合うもの。
“作ってみろよ”のあとには、ふたりで紡ぐ未来が待っている。
それは、家事をめぐる物語でありながら、“人が変わる瞬間”の物語でもある。
現場で幾度も「変わる」人を見てきた私は確信している。
誰かを愛するとは、相手を変えることではなく、
変わっていく自分を、少しずつ受け入れていくことだ。
▼あわせて読みたい
💐女性目線で見る『じゃあ、あんたが作ってみろよ』——“自分を取り戻す”という愛の形
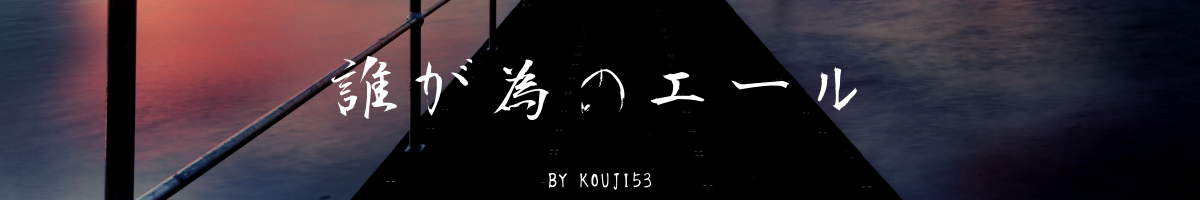

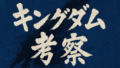

コメント