親としての自分の未熟さと向き合いながら、共に育つ
「親になる」ということは、いつ完成するのか
子どもたちは、毎日少しずつ、でも確実に成長している。
言葉の数が増えたり、昨日できなかったことが今日できるようになったり、ふとした瞬間の表情に「もうそんな顔をするんだ」と驚かされることがある。
そんな変化を目の当たりにするたび、僕は立ち止まってしまう。
果たして、自分はその成長に見合った「親」になれているのか。
父として、ちゃんと導けているのか。
答えはまだ出ていない。
でも、答えの出ないままに、共に歩み続けること。
それこそが「親になる」ということなのかもしれない。
パートナーシップと育児:目を合わせる時間は足りているか
家庭は、夫婦というチームで支え合って成り立っている。
でも現実には、忙しさに追われて、育児に関する価値観や考え方を「話し合う時間」は意外と少ない。
たとえば、子どもを叱ったあと。
妻から「なんで怒ったの?」と聞かれて、うまく言葉にできなかったことがある。
「なんとなく、ちゃんとしてほしかったから」――そんな曖昧な理由しか浮かばない。
もしかすると、子どもとの向き合い方以前に、妻ともっと向き合う時間が必要なのかもしれない。
報告ではなく、共有。
それができてはじめて、家庭はチームとして機能するのだと思う。
本当にあれは怒る必要があったのか?
怒ってしまったあと、必ずやってくる後悔。
「なぜ、あんな言い方をしてしまったんだろう」
「本当にあれは怒るべきことだったのか?」
子どもが泣いたり、黙り込んだりすると、それは伝わった証ではなく、心を閉ざしてしまったサインのように感じる。
特に食事の場面では、それを強く感じることが多い。
僕は、「食べ物を粗末にしてはいけない」という価値観の中で育ってきた。
だからこそ、子どもが「これキライ」と言うだけで反射的に「ダメだよ」と注意してしまう。
ふざけたり、席を立ったり、姿勢が悪かったりすると、つい感情的になってしまう。
でも冷静になって考えてみると、好き嫌いがあるのは当然だし、今は食べられなくても、いずれ食べられるようになることは、自分自身が経験してきたはずだ。
食事に集中できないのも、まだ7歳と5歳の子どもには自然なこと。
さらに言えば、幼稚園や学校でも注意されている中で、家でも同じように言われ続けたら――
「ごはんの時間が嫌い」になってしまうのも無理はない。
自分の中の「こうあるべき」を押し付けてしまう矛盾。
そのことにあとから気づき、反省し、また自分に腹が立つ。
最初から最適解なんて出せるはずがない。
でも、そのことに気づきながら、今日もまた悩み、迷いながら向き合っている。
「これでいいのか」という不安と、それでも前に進むしかない日々
子育てには、正解がない。
だからこそ、不安にもなるし、同時に救われることもある。
SNSや育児本に出てくる“理想の育児”に、自分のやり方が合っているのか不安になることがある。
でも、誰かの「正解」は、自分の家庭にそのまま当てはまるとは限らない。
大切なのは、「我が家の子どもたちにとって、最善の関わり方は何か?」を、常に考え続けること。
迷っていい。悩んでいい。
それでも、子どもと向き合い続けることに意味がある。
「こうなってほしい」と思う自分と向き合う
親として、「こうなってほしい」「こう生きてほしい」という願いは当然のようにある。
でも、その願いが強すぎると、気づかぬうちに「子どもをコントロールしたい」という感情にすり替わってしまう。
子どもは、自分とは別の人格を持った一人の人間。
自分の理想や価値観に合わせて育てるのではなく、
「その子がどんなふうに生きていきたいか」を尊重し、支えられる親でありたい。
信じることは、難しい。
でも、それが愛なのだと、何度も自分に言い聞かせている。
それぞれの「個」としての尊重
家族というのは、ひとつのチームでありながら、同時に「個の集まり」でもある。
子どもも、妻も、自分も、それぞれが独立した人間。
相手の境界線を尊重しながら、つながりを大切にする。
それが家族としての理想であり、人としてのあり方でもあると思う。
子どもに対しても、「親だからこうすべき」と押しつけるのではなく、
ひとりの人間として向き合いたい。
信頼と尊重をベースにした関係こそ、家族の土台になると信じている。
自分が変わることで、子どもも変わっていく
「こうなってほしい」と願うなら、まずは自分がそうあろう。
子どもは、大人の言葉よりも「姿勢」から学んでいる。
働き方、話し方、暮らし方、人への接し方。
子どもたちは、驚くほどよく見ている。
何を言うかより、どう生きるか。
それが子どもにとって、いちばんの“教育”なのだと思う。
子どもとの日々が、親である自分を育ててくれる
絵本を読んでいるときの子どもの顔には、いつも驚かされる。
普段は食事中に立ち歩いたり、気が散ったりしてしまう二人が、
絵本を開いた瞬間、まるで別人のようにおとなしくなる。
物語の世界に集中し、小さな指で絵をなぞったり、言葉に反応したりする姿は、
僕にたくさんのことを教えてくれる。
こちらが子どもの世界に歩み寄れば、ちゃんと心を開いてくれる。
伝え方や向き合い方ひとつで、親子の時間は変わるのだと教えられている気がする。
親歴はまだ7年。
わからないことだらけ。
でも、その分だけ、子どもたちから学べることも多い。
失敗と気づきをくり返しながら、僕もまた、子どもたちに育てられている。
結びに
「親になる」とは、完成することではなく、問い続けること。
正解のない旅の中で、悩み、失敗しながら、
それでも「いま、ここ」にいる子どもたちと向き合っていくこと。
ありがとうと言われる日が来るかどうかは、わからない。
でも、彼らの笑顔と成長が、何よりの答えになっていくと信じている。
親として、ひとりの人間として、今日もまた共に育っていこうと思う。
※これは、7歳と5歳の子どもを育てる「父親7年目」の、ちょっとした独り言です。
同じように迷いながら子育てをしている誰かに、少しでも届けば幸いです。
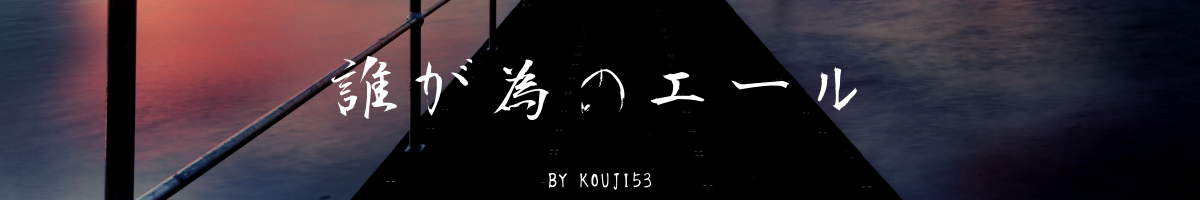
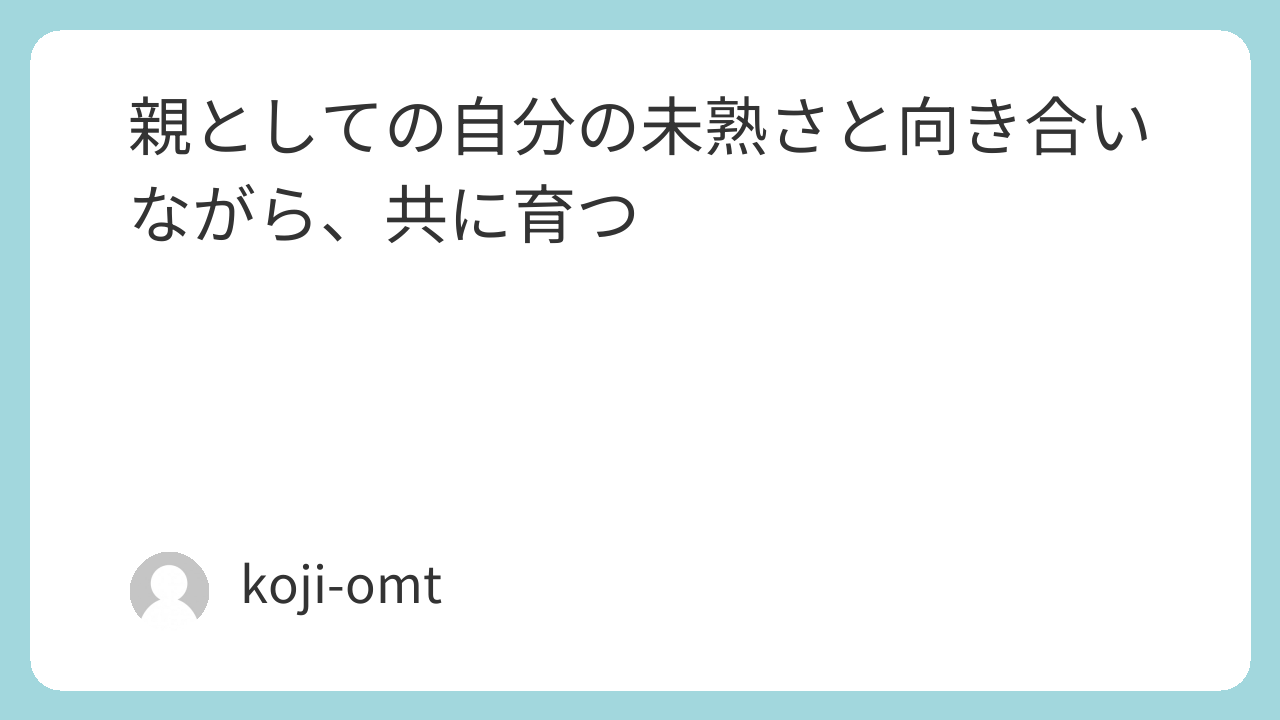
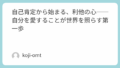

コメント