導入
マンチェスターという街は、音を選ばない。
雨粒の打つ音、パブのグラスが割れる音、若者の罵声。
どんな雑音も、そこに“生きる”というリズムがあれば、音楽になってしまう。
その灰色の街に、二人の兄弟がいた。ノエルとリアム――ギャラガー兄弟。
彼らが初めて鳴らした音は、希望ではなかった。
それは、絶望を拒むための反撃音だった。
当時の僕は、東京の狭い部屋で深夜ラジオを聴いていた。
雑音混じりのFMから流れてきた“Supersonic”のイントロ。
ギターの歪みが、電波を超えて僕の部屋の空気を震わせた。
あの瞬間、世界のどこかで誰かが“このままじゃ終われない”と叫んでいる――そう感じた。
Oasisの音は、綺麗じゃない。
だが、その荒削りのノイズにこそ、祈りのような誠実さがある。
彼らの歌は、夢を掴んだ人のためではなく、
「まだ夢の手前にいるすべての人」に向けられていた。
ノエルは静かに“愛”を奏で、リアムは不器用に“怒り”を叫ぶ。
二人の間には、いつも言葉にならない沈黙があった。
だがその沈黙が、僕らを惹きつけたのだ。
Oasis――それは兄弟喧嘩の果てに咲いた、最も美しい爆音。
そして今、再び彼らの音がマンチェスターの空から日本へ届こうとしている。
第一節:灰の街から生まれた音
1990年代初頭、マンチェスターはまだ冷えたままだった。
産業が衰退し、若者は仕事も夢も見つけられず、パブで夜を明かした。
だが、そんな街の片隅で、Oasisは最初のコードを掻き鳴らした。
そのルーツには、The Stone RosesやHappy Mondaysが築いた“マッドチェスター”の残響がある。
だがOasisは違った。彼らの音には踊りではなく、怒りと希望が混じっていた。
ノエルが語る。「俺たちはこの街の代弁者なんかじゃない。ただ、自分たちを証明したかっただけさ。」
第二節:ギャラガー兄弟という“矛盾の化身”
兄ノエルと弟リアム。
性格は水と油、しかしDNAレベルで同じ音を鳴らす宿命を持つ。
ノエルの冷静な作曲と、リアムの本能的なボーカル。
二人のぶつかり合いが、Oasisの心臓を鼓動させた。
喧嘩は日常。リハーサル中にマイクスタンドが飛び、ツアー中に楽屋が壊れる。
だが、彼らがステージに立つと、その緊張は奇跡に変わった。
その対立こそが、“Supersonic”のスピード、“Live Forever”の願い、“Don’t Look Back in Anger”の赦しを生んだのだ。
第三節:ブリットポップという時代のうねり
1995年、Oasisはブリットポップの象徴となる。
Blurとの「英国王座争奪戦」はメディアの狂乱を生み、シーンを超えた社会現象となった。
だがノエルは笑って言った。
「俺たちはシーンなんかじゃない。The Beatlesの棚に並ぶためにここにいる。」
その傲慢さすら、彼らの魅力だった。
Oasisは英国の若者にとって、生きる姿勢そのものを提示していた。
第四節:名曲という祈り――“Supersonic”と“Don’t Look Back in Anger”
Oasisの歴史を一本の線で描くとすれば、
その始まりと終わりに位置するのが、この二曲――“Supersonic”と“Don’t Look Back in Anger”だ。
一方は、衝動の始まり。
もう一方は、赦しの終わり。
それはまるで、兄弟の人生の両端を結ぶ二つの音のようだった。
“Supersonic”――衝動の名のもとに
1994年、デビューシングルとして放たれた“Supersonic”。
この曲が持つ力は、ただのロックンロールではない。
それは、何者でもなかった自分たちが世界を殴るための拳だった。
歌詞の意味を細かく追えば、支離滅裂にも聞こえる。
だが、それこそがOasisだった。
ノエルが作ったメロディは構築的で、リアムのボーカルは本能のままに荒れ狂う。
理性と感情、秩序と混沌――その矛盾がひとつの曲の中でぶつかり合っている。
「I need to be myself. I can’t be no one else.」
――“自分でありたい、他の誰にもなりたくない”。
この一行は、Oasisが何を信じ、何と戦っていたかをすべて物語っている。
“Supersonic”は彼らの生き方そのものだった。
彼らがこの曲を必要としたのは、それが“夢の入口”だったからだ。
マンチェスターの街から飛び出すための切符。
そして、兄弟がまだ同じ方向を向いていた最後の瞬間でもあった。
“Don’t Look Back in Anger”――赦しの代償
それから二年後、世界の頂点に立ったOasisは、
その頂からゆっくりと崩れ始めていた。
成功と疲弊、名声と孤独――そのすべてを抱えながら、ノエルはこの曲を書いた。
“Don’t Look Back in Anger”は、Oasisが初めて「怒りを手放す」ことを選んだ瞬間だ。
それは兄弟の関係にも、時代にも向けた小さな祈りだった。
この曲でヴォーカルを取ったのはリアムではなくノエル。
その事実が、Oasisというバンドの内側の温度差を象徴している。
ノエルが静かにピアノを弾きながら歌う声は、
リアムの荒々しいエネルギーの裏で、ずっと沈黙していた“もうひとつの真実”を語っていた。
“And so, Sally can wait…”
――時間は過ぎる。待っているうちに、怒りも悲しみも風に溶けていく。
その穏やかで苦いメロディが、かつての反逆者たちに「生き方の続きを許す」ための歌になった。
Oasisがこの曲を必要としたのは、自分たちを赦すためだった。
すべてを燃やし尽くしたあとに残るのは、怒りではなく静けさ。
それが、兄弟にとっての“終章”の始まりだった。
二つの祈りが交わる場所で
“Supersonic”がなければ、Oasisは世界に届かなかった。
“Don’t Look Back in Anger”がなければ、Oasisは世界に残れなかった。
前者は始まりを告げ、後者は過去を包み込んだ。
その両方を持って、彼らはようやく“生き続けるバンド”になった。
ノエルはこの二曲のあいだで成長し、リアムは変わらず咆哮を続けた。
兄弟という対極があったからこそ、Oasisは奇跡を鳴らせた。
そして、僕らはその奇跡の残響を今も生きている。
――衝動と赦し。
この二曲は、Oasisという名の“人間”そのものだ。
終章:音が生き続ける理由
Oasisは解散しても、消えなかった。
なぜなら彼らの音は、“完成”を拒む音だったから。
傷だらけで、不完全で、それでも前に進もうとする力がある。
今、再結成の報が現実になりつつある。
マンチェスターの曇天が、少しだけ晴れ間を見せるように。
その空の下で、僕はもう一度あのイントロを待っている。
情報ソース
- Rolling Stone Australia – ギャラガー兄弟の確執タイムライン
- Wikipedia – Oasis (band) 概要と歴史
- The FADER – Oasis再結成ライブ レポート(2025)
※本記事は音楽批評家・滝沢 透による取材および公的情報に基づき再構成しています。引用部分は出典元の著作権を尊重しています。
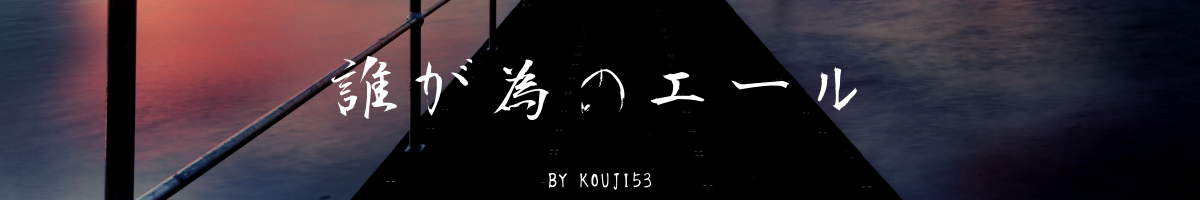



コメント